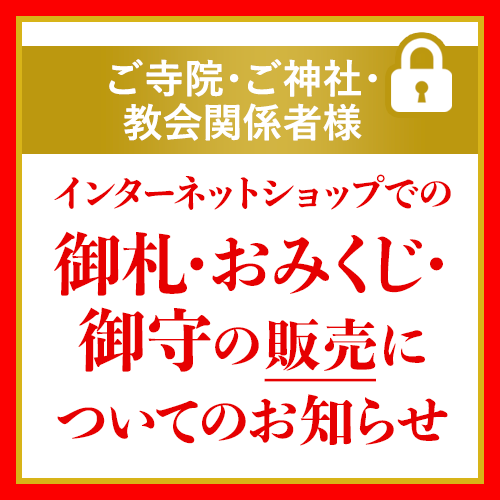交流の広場「微笑苑」 001-010
第一話 商いの心得

江戸時代の商人がいかにあるべきかを説いた本に西川如見という人が書い た「町人嚢(ぶくろ)」という名著があります。
江戸時代は、士農工商という身分制度があり、商人は、低い身分に置かれて いました。
当時は、武士が世の中を支配していた時代ですから、武士は商人が力 を持つことを最も恐れていたのでしょう。
だから「商い」とは、つまらぬ仕事だ、悪どいやつのすることだと世論を意識的に操作していました。
そんな風潮の中から作り出されてきたのが「商人と屏風は曲らねば立たぬ」 という言葉です。
たしかに屏風は曲がらなければ立ちません。
しかし、商いを生 業として生きる人々を揶喩するように使われたのではたまりませんね。
そこで 如見はその著書で、こんな風に反論しています。
ある日、古い屏風の精が、一人の商人の夢の中にあらわれました。
そしてこういうのです。
「常日頃、わしは人間から曲ったものだといわれるのが、口惜しくてた まらない。
わしは曲っているのではない。
考えてみろ、屏風が開きぱなしになった ら、立ってはいられない。
閉じてしまっても倒れてしまう。
開き過ぎもせず、閉じ 過ぎもせず、その中ぐらいにあるというのは、仏の教えでいう中道をわしが心得 ているからだ。
お前は、屏風に喩えられて落ちこんでいるようだが、これはむしろ商人の徳分と思って誇りにした方がよい。
それより大切なのは、商いをする 時、曲った場所に気をつけることだ。
どんなに立派な屏風でもデコボコした所 では、立つことはできない。
左様に心得て商いに励め」屏風の精を使って商人の プライドと有るべき様を説く如見はまた、「商いとは、耐え忍ぶことであり、信 用であり、飽きないで努力することである」とも説いています。
そして謙虚さこ そ商人の守るべき道であると言うのです。
「だからでしょうか。今でも福の神として人気の高い大黒さまについて、こんなことが言われています。
「大黒さんが、色の黒いのは、着飾ることに心を奪われ るなという戒、丈の低いのは、身を低くしろということ、袋をかついでいるのは、他人の身を養うため、打出の小槌は、道具を手放すなという教え、米俵の上に 立つのは、生命をつなぐ米こそ第一の宝ということである。
昔から、橋の板で作った大黒さんが霊験あらたかと言われているが、それは橋が広く万民を渡し、人から踏まれても文句をいわない徳分を持っているからだ」と、ここまで説けば、商いの道も立派な仏道修行だと言えるのではないでしょうか。
それこそ釈迦の説法だったかわかりません。
- 2022.07.14
- 13:06
第二話 素晴しき靴みがきの青年

ぜひ、長谷川如是閑さんという人のエピソードを紹介させてください。
長谷川さんは新聞社に務めていた人です。
六十年あまり前の敗戦の混乱期、人々の心もすさんでいた頃の話です。
ある日、長谷川さんが、東京のお茶の水駅に降りた時のこと、汚れていた靴をきれいにしようと見回すと、ちょうど駅前に靴みがきの青年がいました。
「みがいてくれ」と言って足を出すと、青年は「はい」と返事をして、ハケで靴の埃を払ってから言いました。
「旦那さん、すばらしい靴ですね。こんな皮は、今の日本にはありませんよ。
私の持っている靴墨を付けたら、せっかくの皮がかえって駄目になってしまいます。
どこかちゃんとした店に行かないと、この皮に付ける靴墨はありませんよ」と、なんと磨くのを断わったのです。
びっくりしたのは長谷川さんです。
断わられたのは始めて。
でも「そんなこと言わんで、僕は急ぐんだから、ちっともかまやせん。やってくれ」とたのみ ました。
でも青年は、「いや、私は靴みがきですが、自分の良心に恥じる仕事はできません。この皮には私の靴墨は付けられません」と言ってガンとして受けつけません。
それならと、長谷川さんはポケットから小銭を出して、「少ないが取っておいてくれ」と言うと、彼は、「私は仕事もしないのに、お金はいただけません」と、どうしても断わります。
仕方なく礼を言うと、長谷川さんは先を急ぎました。
でも、この靴みがきの青年のまっ正直な気持ちがうれしくてたまらなかったのです。
感激した長谷川さんは、さっそく翌朝の新聞に、『日本未だ亡びず』と題して、昨日の出来事を書き、「彼のような青年たちがいる限り、日本は大丈夫だ」と主張したのです。
ところで、二、三日経った日のこと、一人の大学生が長谷川さんに面会に来ました。
よく見るとあの靴みがきの青年です。
彼はあの記事の載った新聞を、できるだけたくさん買うと、自分のこととは一切言わず、靴みがきの集まりで読ませたそうです。
そして、靴みがきの仲間のこんな行いもニュースになるんだ。
みんなも負けない様、日本再建のためにも頑張ろうと訴えると、皆が涙を流して「やろうやろう」と誓ってくれたというのです。
長谷川さんは、またまた感激し、これを記事にしました。
良心に恥じない勇気のある行いを、お経の言葉では「勇猛精進(ゆうみょうしょうじん)」と言います。
この青年の行いを、きっと仏さまも、ほほえんで見ておられたことでしょう。
- 2022.07.14
- 13:06
第三話 お釈迦さまへの手紙

それは木枯らしが吹く、大正十二年の暮れ近くのことでした。
その年の九月一日、関東大震災が起こり、東京は半分以上が焼野原の廃墟となってしまいました。
この大震災で家族を失ってしまった獅子谷虎象さんは、上野のバラック長屋で代書屋さんを開いていたのです。
代書屋さんというのは、役所や裁判所等の届け書や、字の書けない人たちのために、手紙や葉書を代わって書いてあげる仕事をする人です。
ところが、虎象さんは、その一風恐い名前のせいでしょうか、サッパリお客がありませんでした。
「場所が悪いのかなあ」などと思案しているところへ、一人の男の子が飛びこんで来たのです。
「おじちゃん、手紙書いてくれる」
そう頼む少年に、小さくてもお客さんは、お客さんだと思った虎象さんは「いいよ、どこへ出すんだい」と尋ねました。
「インドのおしゃかさま」これを聞いた虎象さん、びっくりして「大人を馬鹿にする気か」と怒鳴ろうとしましたが、あまりにその幼な子の目が真剣なのに、思わず言葉を呑み込んでしまいました。
「ぼく、おしゃかさまに、お母ちゃんの目をさましてもらうように頼みたいんだ。そしてご飯を作ってくれるようにお願いするんだ」
これはただ事ではないと思った虎象さん、男の子に事情を聞くと、お母ちゃんはずっと寝たきりだったけど、今朝になって、いくら呼んでも目をさましてくれないとのこと、お腹もペコペコになり、誰かに頼もうと思ったら、ふとお釈迦さまのことを思い出したと言うのです。
「だってお母ちゃんが、いつも困った時には、おしゃかさまにお願いしなさいって言ってたもの。でも地震でボクん家(ち)のお仏壇も焼けてなくなってしまったでしょう。だから、おしゃかさまに手紙を書いてもらいたいんだ」
すべてを察した虎象さんは、少年を抱きしめると「分かったよ、坊や。おじちゃんがちゃんと書いてあげる。坊やのお母ちゃんが目をさますように、坊やが温かいご飯がたべられるようにってね」と約束したのです。
そして、この約束は本当になりました。
虎象さんは、男の子の家に行って、亡くなったお母さんのお葬式を出してやり、少年を自分の子として引き取ったからです。
虎象さんは少年に言いました。
「お釈迦さまがすぐ返事をくださってね。お母ちゃんは体が弱いから、天国でゆっくりと休ませてあげるって。その間、坊やは、おじさんの家で元気で待っていなさいって。分かったかい」
コックリうなづく少年を見て、虎象さんもお釈迦さまに「私もこれで、生きる希望がわきました」と心からお礼を言ったそうです。
- 2022.07.14
- 13:06
第四話 お寺の奥さん

「 寺庭婦人 という言葉から、どんなイメージが浮かぶ?」と尋ねたら「お寺の庭掃除のおばさん」という返事が、女房から返って来た。
もう少し品のいい答えを期待していたのに。
女という生き物は、現実的なのだろうか。
「お寺の嫁さんになったら、奥さん奥さんと呼ばれて結構な身分ですよ」そんな仲人の口車に乗って私と一緒になった彼女の生活実感がそう言わせたのかもしれない。
休みらしい休みもない、自由もない。
おまけにお寺は、私物じゃない。
「これじゃ人手不足を解消するために、お嫁に来たようなものね」と女房は言う。
まさにその通りと言えなくはない。
しかし、それに同意すれば「そんなつもりで結婚したの」と、十何年来の恨みが返って来る。
ここは何とかして「寺庭婦人」という立場に付加価値をつけなければ、私の身があやうい。
そこでお寺の奥さんを意味する言葉を調べてみることにした。
すると「梵妻(ぼんさい)」、「大黒(だいこく)」、「坊守(ぼうもり)」という三つの言葉に出食わした。
「昔、坊さんは結婚できなかったんじゃないの」と横で女房が言う。
その詮索はこの際、置いておこう。
戒律がどうであれ、歴史的には、女性が寺の中に居た事実が、言葉の中に証明されているのだから。
しかも「梵妻」の「梵」は「きよらか」という意味、もっと深くは「宇宙の根本真理」という意味さえある。
誰が付けたのかは知らないが、素晴らしいネーミングじゃありませんか。
坊さんだって男、その胸の内が伝わって来る気がする言葉だ。
つぎは「大黒」、いわゆる福の神の大黒さまである。
大黒さまは天台宗の伝教大使が、比叡山でお祀りしたのがその始まりだと言うが、この神さまは、お寺を守り、生産を司る役目があるという。
そして「坊守」は、読んで字のごとく、お寺を守る人という意味だ。
今でも真宗では、住職の妻たちは「坊守さん」と呼ばれている。
いずれにしても、女性が寺に入った時、そのパワーが絶大であることは間違いない。
だから、寺庭のご婦人たちよ。
法のため、寺のため「梵我一如」の精神で、住職に協力していただきたい。
ただそう願うばかりなのである。
- 2022.08.08
- 11:58
第五話 女房の『寺庭だより』

女房が〈寺庭だより〉を出しはじめて、早二年になる。
ハガキに、その月々に思ったことを書き、コピーをして、檀家の婦人会員に送っているが、なかなか好評だ。
毎月の掃除や、婦人会の行事にどうすれば出席者が増えるかと考え、思いついたそうだが、目に見えてその効果はあった。
この一年でその数は倍になったのである。
それどころか、出席はできないけれど、ハガキだけは毎月欲しいという波及効果まで現われ、ご本人は大いに満足しているようだった。
しかしその頃になると、今度は書く事に行きづまる。
「ああ、余計な事始めなきゃよかった」そうボヤく女房に「俺が代わってやろうか」と言うと「みんな、私の便りを待っているのよ、あんたの文章を読みたいわけじゃないわ」とつっぱった。
ナルホド、そうかもしれない。
これは 住職の便りではないところがいいのだろう。
貰った方も、宛名が主人ではなく、夫人であるのが嬉しいのかもしれない。
女同士の連帯感が生まれようとしているのなら、こちらの入りこむ余地はなさそうだ。
そう思っていたら、檀家に出かけた時、そこの奥さんから「さすが、お寺の奥さんですね」と言われた。
「私、断然ファンになりました。もう、和尚さんはどうでもいいです。これからはお寺も女の時代、私たちも頑張りますよ」こんな発言が出て来ればシメタものである。
女房のことをほめられたのも嬉しいが、みんなをヤル気にさせているのが、なんとも頼もしい。
住職といっても、寺にじっとしておれないのが、現実の住職。
それならば、寺に尻をどっしりと構え、守っていくのは、むしろ住職の妻の役目だと言った方が正しいのかもしれない。
そんな女房が今年の春出した〈寺庭だより〉には、こんな息子との対話がネタになっていた。
「夕方、息子が学校から帰って来て『お親爺さんは?』と尋ねたので『ちょっと人生相談に出て行ったよ』というと『そんなの俺に聞けば、すぐ答えてやるのに』と言いました。
そこで『あんたなら何て答えるの?』と聞いたら『人生、悩んだって始まらん。生命があるだけ丸もうけ』とすました顔。
思わず、こちらがドキリ。
丸もうけの生命を大切に そんな気持で、お彼岸を迎えましょう」
これを読んだ総代の爺さんから「奥さん、これ、あんたが本当に書いたのか?息子さん、こんな事、本当に言ったのか?」と電話があったりで、大ヒット。
こうなると 「大変だけどやり甲斐もあるわね」と本人もハッスルした。
そして一ヶ月後、私が交通事故に遭うというお寺にとっては大事件が突発した。
以来、お盆も住職不在というピンチが続いた。
私は、今や人生相談の解答者どころか、質問者という気分にまで落ち込んでしまっている。
そんな時、「生命があるだけ丸もうけ」と言うあの母子の対話が、頭に浮かんだ。
ベッドの上では素直になる他、道はないのかもしれない。
- 2022.07.14
- 13:07
第六話 遠くて一番近い所

檀家に、弁護士がいる。
高校の一級後輩だが、大学に行く時には同輩だった。
その彼が「この間、和尚に教えてもらった言葉で、従弟の嫁を慰めました」と言った。
彼の親爺さんが亡くなってから檀家になったのだが、それ以来、昔馴染みの「ジュンちゃん」でなくて、「和尚」と言う呼び方で接してくれる。
いかにも法律家らしいケジメのつけ方だが、いい加減な私にとっては、時として窮屈にもなる。
そこでこの日も「へぇ、俺が教えたって、どんな言葉?」と、ぞんざいな言い方で、これに対応した。
すると、彼のネクタイを締めたような顔が、バンカラを気取っていた大学の頃の顔に戻った。
彼には高校の時、柔道部でシゴキ事件を起こし、停学処分を食らった前科があるのだ。
余談はさて置き、私のこの言葉に「ほら、親爺が死んだ時、俺に言ってくれたじゃないですか」と、じれったそうに言った。
噛みつかれては大変と、思い出そうとしたが、いつもいろんな人間に、口から出まかせを言っているので、とんと記憶にない。
「一番遠い所は、一番近い所だと言うあの話ですよ」
と言われても、まだ私の脳ミソは何も反応しなかった。
それを察してか「実は医者をしていた従弟が先日亡くなりましてネ」と彼は話を転じた。
「自分で知っていたんですが、ガンでした。すごくいい男だったんです。それだけに嫁の気の落としようといったら、見るも哀れだったんです」
年老いた両親に先立ち、妻子を残して往った一人の男の無念さは、ほぼ同年代である私にとっても痛いほど分かる話である。
「だから亡くなった人は遠い遠い仏さまの世界に旅立ったけど、その世界は一番近い所にあるんだよと言ったんです」
「一番近い所って?」
「いやだな。自分が僕に言ったんじゃないですか。その人の背中だって。宇宙はまっすぐに前を見つめれば、行きつく所は自分の背中になるんだって。
だからご先祖は背後霊として、いつも側にいると教えてくれたのは、和尚、あなたですよ」こう言われて、なんとか思い出した。
彼の親爺さんが亡くなって、彼があまりにも力を落としていたから「死んだ人は、どこにも往きはしない。いつも生きた人間と一緒なんだ」と言って慰めたことがあったっけ。
その言葉を、そんなにまで大切にしてくれていたとは。
そう感激して肯くと「そう信じたいという気持ちが、僕にもあったんでしょうね。
あれから素直に手が合わせられるようになりましたから」とも言った。
その彼が、今度は他人にこの言葉を伝えてくれたのである。
- 2022.07.14
- 13:07
第七話 息子の荒行

息子が百日間の “荒行” に初めて挑戦し、無事、修行を終えて帰ってきました。
髭(ひげ)は、私に似て余り濃くありませんが、それでも一まわり大きくなった気がします。
そう話すと、「やっぱり親馬鹿だね」と笑われました。
でも笑われようと、馬鹿と言われようと、親は子供の成長した姿が、何よりも嬉しいものです。
私が初行に入行したのは、二十六年前、その時の苦しい思い出があるだけに、息子の辛さも手に取るように分かるのです。
修行中、息子のことが心配になって、一度だけ面会に行きました。
息子は思いのほか元気でしたが、足は座りダコが破れ、大きな穴が二つもあいていました。
「それくらい、たいしたことはない」と励ましたものの、私は顔をそむけました。
出かかった涙を見られたくなかったからです。
修行を志せば、誰もが体験することだとは知りながら、我が子のこととなると、こうも胸が痛むものなのでしょうか。
実は、私が二度目に荒行堂に入った時、初行さんたちの教育係になったのです。
眠い、寒い、ひもじいという三つの苦しみの中で、疲れてしまった初行さんたちはバテそうになります。
そんな時、喝を入れ、初行さんをシゴかなければならないのが私の役目でした。
教育される方も大変でしょうが、教育する方も大変なのです。
相手になめられたのでは、ちゃんとした指導はできません。
そこで私なりの工夫をしました。
怠けたり、間違いを犯すと、一日に七回の水行の他に、罰として与えるスペシャル水行を考え出したのです。
その “スペシャル罰水” が今になっても残っていようとは思いませんでした。
「いいか、これを考えついたのは、お前の親爺だそうだからな。俺を恨むなよ」、そう言って先輩さんから罰水を受けた息子は、「なんて親爺だ、ぶん殴ってやりたくなった」と思ったそうです。
もっとも、そんな気持を息子が語ったのは、めでたく百日間が終わってからのことです。
まさか、めぐりめぐって、そんなできごとがあろうとは!
『親の因果が子に報い』と言うのは、こんなことを言うのでしょうか。
しかし、そんな先輩さんのシゴキに会ってこそ、息子が逞しくなったのも事実なのです。
お坊さんのことを “出家” と言いますが、温かい家庭や、親子の甘い関係を離れてこそ、人は自分の人生を切り開く覚悟ができるものです。
お釈迦さまは、それを私たちに気づかせるために出家という道をお説きになったのかもしれませんね。
親である私は、今、しみじみそう感じています。
- 2022.07.14
- 13:07
第八話 愛、その切なさ

人を愛することは、なによりも素晴らしいことです。
ところが、愛するが故に、私たちは人間として、もっとも愚かな部分を思い知らされるということもあります。
たとえば、私は誰よりも自分の子供たちを愛しています。
仏さまが「愛することは、迷いのもとだ」とおっしゃろうとも。
でも、その大切な子供を、立派に育てたいと 思ったら、やはり仏さまの教えを素直に聞かなければならないのかなと思うことがあります。
クリスチャン作家として有名な曽野綾子さんが、かつてこんな話を紹介していました。
それは、今から五十年ほど昔の朝鮮戦争の時のこと、一人の若いアメリカ兵が、負傷し本国に送還されることになりました。
故郷では、息子の無事を祈って両親が、その帰りを待っています。
本国に着いた彼は、病院から家に電話をしました。
電話に出たのは、お父さんです。
息子の声を聞いたお父さんは、大喜びで「すぐに病院に迎えに行くから」と答えました。
その時、息子は「パパ、実は、ぼくの他にもう一人、友達がケガをしてね。彼はぼくよりも、もっとひどいケガなんだよ」と 話しました。
「どんなケガだ」と聞くと「両足を切り落されている」と答えました。
「お願いだから、パパ、彼も家に連れて帰ってくれないかな、彼には身寄りがないんだ」そう頼む息子に「いいとも」と答えたお父さん。
すると息子は「一生面倒みて やってほしいんだけど」と頼みます。
我が子のことなら、兎も角も、そんな他人の子供までもと思ったお父さんは「そんなことは無理だよ」といって電話を切ると、急いで病院まで車を飛ばしたのでした。
ところが、そこに待っていたのは、愛する息子ではなく、愛する息子の遺体だったのです。
お父さんは「なぜ?」と絶叫しました。
そして、驚くべきことを知らされたのです。
両足を失ったのは、友達ではなく、息子自身であったということを。
彼は、電話をし終った直後に自ら命を絶ったというのです。
再び「なぜ?」とお父さんは叫びました。
息子からその答えが聞かれるはずもありません。
ひょっとしたら、彼は、親をいきなり悲しませたくないために、そんな手を使おうとしたのかも知れません。
でも、お父さんは「我が子を愛するように、他人の子をも愛する気持ちがあったならば」と涙を流したそうです。
愛するが故の悲劇、この話の中に、私は「愛」という心のむつかしさを教えられる気がしたのです。
- 2022.07.14
- 13:07
第九話 お経の貯金

「布施なき経を読め」という言葉がある。
坊さんがお経を読めば、檀信徒はお布施を出す。
そのお布施で我々坊さんは生 活もし、家族も養っているのだから、お布施はありがたい収入源でもある。
しかしそれを、いわゆる労働に対する報酬とのみ考えるならば、我々は大きな 落とし穴に落ち込んでしまうだろう。
布施は「ほどこし」とも言い、「自分が他に対してできる事をさせてもらう歓び」を意味する、仏教で非常に大切な実践徳目である。
それがいつの間にか、坊さんの「ギャラ」を意味する言葉に堕してしまった。
まことに恥ずべき事だと言えよう。
冒頭に挙げた言葉は、そんな坊さんの反省から生まれて来た言葉ではないだろうか。
私自身、先輩から「お経の貯金をしておかないと、罪障にやられるぞ」と言われた事が何度かある。
罪障とは、自分が犯す罪や、他からこうむる障害の原因を言うのだろうか。
「他人から頼まれて読むお経はあくまで他人のため、自分の徳にはなってないと肝に銘じておけ」
今となってはその言葉が身に沁みるが、当時は頭の上を素通りしていたなぁ。
檀家まわりをして、日に何遍も読んでいるのに、「それ以上お経が読めるか。」そんな気持でいた。
だから師父が朝のお勤めをしていても「親爺がやってくれているから、それでいい」と自分は朝寝をし、ずぼらを決め込んでいた。
それが二十数年続いていたのだから、私の罪障は溜まりに溜まっていたかもしれない。
晴れて師父から、住職の座を譲られた時、さすがに私も「今日からは、朝のお勤めをするぞ」と決意した。
しかし、それは何日続いただろうか。
原稿書きで夜遅くなったと言ってはサボリ、会議で疲れたと言い訳しては、女房に相手をさせて、その場凌ぎをする日々もあった。
その結果とは言いたくない。
しかし、私が交通事故で病院に運ばれたと聞いた時、女房は思ったそうだ。
「住職なのに、朝のお勤めをちゃんとしないからだ」と。
実は私も、入院中、そんなざんげの気持を起こしていたのである。
「そんな事、恥ずかしくて檀家の人には言えんだろう」二人っきりになった時、私たち夫婦は語り合った。
「でも助かったのは、やっぱり仏さまのお陰よね。いくら偉そうな事を書いても、自分が実行できなけりゃ誰もついて来ないのよ」
女房が、「布施なき経」の真意を知るはずはない。
しかし、亭主のだらしない態度に、いつの日か、仏さまの戒めがあるとは予感していたのかもしれない。
布施とは、報酬がなくても自分のする事に歓びを感じる事だと書いた。
檀信徒の財施に対し、坊さんには法施という言葉が用意されている。
法施とは、早い話が、仏の教えを人々に伝えることである。その行いなくしては、我々僧侶は、坊さんの資格を失なってしまうだろう。
まず、朝のお勤めは、ちゃんとしようごく当たり前の事なんだが、今の私には、それしか言えないのである。
- 2022.07.14
- 13:08
第十話 心の宝珠

聖書に「人はパンのみにて生きるにあらず」という名言があります。
これは、人間は、物質的な欲望のみで生きてはならない。
魂の目覚めがなければ、本当の人生とはいえないという教えです。
ところが、どんなに教えが有りがたくても、そればっか りでは、ちっとも腹の足しにはならないと反論する人もいます。
たしかにその通りで、生きている悩みは、心と物の両方から起こってきます。
そんな時、私は観音さまが手に持たれている〈如意宝珠〉のことを思い浮かべます。
如意宝珠とは、願いごとが、そのままに叶えられる宝の珠という意味です。
そんな珠が実際にあったら、どんなに素晴らしいだろうなと思います。
でも、もしそれ を手に入れたら、信仰心はなくなるのではないかとも考えるのです。
坂村真民さんの〈ねがい〉という詩をご紹介しましょう。
「救世観音さま/あなたが両手で/しっかとお持ちになっておられるのは/なんでしょうか/美しい珠でしょうか/それとも/おいしい握り御飯でしょうか/いまのわたしには/何かそんな食べるものの方が/強く思われて/朝夕あなたのお姿を拝んでおります/救世観音さま/わたしが亡くなりましたあとも/この三人の子供たちに/あなたの温かい/おん手のおにぎりを/恵み与えて下さい/どんな生き死にの/苦しい目にあっても/母と子が飢えずにゆく/一握りの/貴い糧を/分かち与えて下さい」
真民さんがこの詩を詠んだのは、戦後まもない頃、頼るべき人もいない四国の片田舎で職を求めていた時だそうです。
仏教詩人として名高い真民さんでさえ飢えの苦しみの中からは、一握りの御飯を求めました。
観音さまの如意宝珠が温かいおにぎりに見えたのです。
誰が、それを責めることができましょう。
いえ仏教詩人なればこそ、こんなにも素直に、自分の苦しみを訴えることができたともいえます。
「私が死んでも残された妻と子に一握りの貴い糧をお与え下さい」と手を合わせる祈りの中に無限のやさしさを感じます。
同じ頃、発表した詩の中に
「かなしみは/みんな書いてはならない/かなしみは/みんな話してはならない/かなしみは/わたしたちを強くする根/かなしみは/わたしたちを支えている幹/かなしみは/わたしたちを美しくする花」
という言 葉があります。
真民さんは、苦しみの中から如意宝珠を磨きだした人だと思うのです。
- 2022.07.14
- 13:08