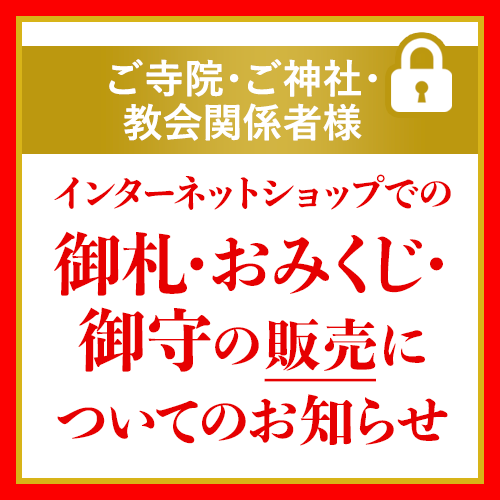蓮の実通信
No.030 「消えざる恨み」
他人に冷たい仕打ちをされた時、私たちは「死んでも忘れるものか」と相手を怨むことがあります。怨みは、古今東西、たいそう始末の悪いもので、人間の歴史は、その怨みの繰り返しと言われるほどです。
試みに、お経をひもといてみると、お釈迦さまのこんな言葉に出会いました。
『<彼、われを罵り、彼、われを打ちたり。彼、われを打ち負かし、彼、われを奪えり>かくのごとく心執する人々に、怨みは、ついにやむことなし』
きっとお釈迦さまのもとにも、忘れられない怨みをかかえた人が、自分の胸の内を聞いて欲しいと集まって来たことでしょう。そんな悩める人々に、お釈迦さまは、どのように答えられたのでしょうか。
私は、そんな思いにふけりながら、ある戦争の未亡人のことを思い出したのです。
敗戦後しばらくは、国民の誰もが、食糧の危機にさらされた時期です。二人の幼な児をかかえた彼女の毎日は「この子たちを、ひもじいめに遭わせたくない」という思いだけでした。売れる物は全部売り、とうとう底をついてしまった時、彼女は最後の綱と、本家の門を叩いたのです。ところが対応に出た義兄嫁に、ケンカもホロロに「その格好は何なの。食べ物が欲しいなら、裏にまわって納屋のカボチャでも持っていくがいいわ」と冷たくあしらわれた彼女は、くやしさのあまり、二人の子の手をぎゅっと握りしめ、逃げるようにして本家を後にしたそうです。
「こうなったら、誰も頼るものか。いつか本家を見返してやる!」そう誓って生きて来た三十余年、その甲斐あって二人の子も立派に成長し、孫にも恵まれ、家も建て直すことができるようになりました。そして、古い家を解体する時、彼女はお経をあげてくださいと、私のいるお寺にやって来たのです。
「考えてみれば、この家は私の怨みの思いでいっぱいです。義兄嫁のあの言葉があればこそ、今日があるのですが、それを許してしまえるほど、私は人間ができていません」と語る彼女の記憶の中に、今なお残るあの日の屈辱。それを払おうとして払えないと思い知った時、彼女はやはり仏さまのお慈悲にすがるしかないと思ったのでしょう。
『まことに、怨みごころは、いかなるすべを持つとも怨みをいだくその日まで、人の世にはやみがたし。怨みなさによりてのみ、怨みはついに消ゆるべし。これかわらざる真理(まこと)なり』お釈迦さまは、彼女の心を見透かすかのように、こう語りかけていらっしゃるのです。
(W)

試みに、お経をひもといてみると、お釈迦さまのこんな言葉に出会いました。
『<彼、われを罵り、彼、われを打ちたり。彼、われを打ち負かし、彼、われを奪えり>かくのごとく心執する人々に、怨みは、ついにやむことなし』
きっとお釈迦さまのもとにも、忘れられない怨みをかかえた人が、自分の胸の内を聞いて欲しいと集まって来たことでしょう。そんな悩める人々に、お釈迦さまは、どのように答えられたのでしょうか。
私は、そんな思いにふけりながら、ある戦争の未亡人のことを思い出したのです。
敗戦後しばらくは、国民の誰もが、食糧の危機にさらされた時期です。二人の幼な児をかかえた彼女の毎日は「この子たちを、ひもじいめに遭わせたくない」という思いだけでした。売れる物は全部売り、とうとう底をついてしまった時、彼女は最後の綱と、本家の門を叩いたのです。ところが対応に出た義兄嫁に、ケンカもホロロに「その格好は何なの。食べ物が欲しいなら、裏にまわって納屋のカボチャでも持っていくがいいわ」と冷たくあしらわれた彼女は、くやしさのあまり、二人の子の手をぎゅっと握りしめ、逃げるようにして本家を後にしたそうです。
「こうなったら、誰も頼るものか。いつか本家を見返してやる!」そう誓って生きて来た三十余年、その甲斐あって二人の子も立派に成長し、孫にも恵まれ、家も建て直すことができるようになりました。そして、古い家を解体する時、彼女はお経をあげてくださいと、私のいるお寺にやって来たのです。
「考えてみれば、この家は私の怨みの思いでいっぱいです。義兄嫁のあの言葉があればこそ、今日があるのですが、それを許してしまえるほど、私は人間ができていません」と語る彼女の記憶の中に、今なお残るあの日の屈辱。それを払おうとして払えないと思い知った時、彼女はやはり仏さまのお慈悲にすがるしかないと思ったのでしょう。
『まことに、怨みごころは、いかなるすべを持つとも怨みをいだくその日まで、人の世にはやみがたし。怨みなさによりてのみ、怨みはついに消ゆるべし。これかわらざる真理(まこと)なり』お釈迦さまは、彼女の心を見透かすかのように、こう語りかけていらっしゃるのです。
(W)

No.029 「別れのご挨拶」
友人から聞いた、ちょっと心に浸みる話をご紹介します。
ある日、彼の家では、お婆ちゃんの十三回忌を営むことになりました。約束の時間になり、和尚さんがやって来ました。ところが、いつもと違って、和尚さんは、二人連れです。「どうしたのかな?」と思って迎えると、「ちょっと体調を崩しておりますので、息子に連れて来てもらいました」と言って、お仏壇の前に座ったそうです。
「その日のお経は、気のせいか、今までで、いちばん有り難いお経だったよ」、友人はそう言っていました。
さて、お勤めもとどこおりなく終わり、家族の皆が頭を下げ、お礼を言った時のことです。お茶をおいしそうにいただいた和尚さんが、皆の顔を見わたすようにして言い出しました。
「これで、お婆ちゃんへのご挨拶も済んだことだし、今日はひとつ皆さんに、私の気持ちを聞いていただきましょう。実は、私は昨年、直腸ガンになりましてネ、手術で悪い所を全部とってもらいました。ヤレヤレこれで大丈夫と思っていたのですが、今度は、肝臓に転移していることが分かりました。そこでまた、手術をして、今はなんとか落ち着いてはいます。でもお医者さんは、いつ再発するかも分からないとおっしゃっています。いわば、死の宣告をされているに等しい状態です。私は、お坊さんですが、皆さんと同じ凡人です。その言葉を聞いた時には、本当に悩みました。そして残された時間をどう生きればいいのかと、ずいぶん考えたのです。まわりの人は、息子も一人前になったから、すべてを息子にまかせて、のんびりしたらと言 ってくれました。でも、明日が分からない生命だから、のんびりなどできないと思ったのです。今までお世話になった人、ご縁を繋いだ方々に一人でも多くご挨拶してこの世を去りたいと思うようになりました。だから、こちらのお婆ちゃんの十三回忌にも是非お伺いして、今までのご恩に対してお礼を申し上げたかったのです。ひょっとすれば、私の生命は十七回忌の時までいただけるかもしれません。でも明日を頼むより、今日を精いっぱいに生かさせていただけるのが、今の私には何よりもありがたいのです」
こう言って、手を合わせた和尚さん。その姿を見て、「俺とっても感動したよ。あの和尚さんは、命がけで、うちの婆ちゃんにお経をあげてくれたんだよな」と友人は話したのです。
きっと、そこには、生と死を越えた絶対安心の仏さまの世界があらわれていたに違いありません。
(M)

ある日、彼の家では、お婆ちゃんの十三回忌を営むことになりました。約束の時間になり、和尚さんがやって来ました。ところが、いつもと違って、和尚さんは、二人連れです。「どうしたのかな?」と思って迎えると、「ちょっと体調を崩しておりますので、息子に連れて来てもらいました」と言って、お仏壇の前に座ったそうです。
「その日のお経は、気のせいか、今までで、いちばん有り難いお経だったよ」、友人はそう言っていました。
さて、お勤めもとどこおりなく終わり、家族の皆が頭を下げ、お礼を言った時のことです。お茶をおいしそうにいただいた和尚さんが、皆の顔を見わたすようにして言い出しました。
「これで、お婆ちゃんへのご挨拶も済んだことだし、今日はひとつ皆さんに、私の気持ちを聞いていただきましょう。実は、私は昨年、直腸ガンになりましてネ、手術で悪い所を全部とってもらいました。ヤレヤレこれで大丈夫と思っていたのですが、今度は、肝臓に転移していることが分かりました。そこでまた、手術をして、今はなんとか落ち着いてはいます。でもお医者さんは、いつ再発するかも分からないとおっしゃっています。いわば、死の宣告をされているに等しい状態です。私は、お坊さんですが、皆さんと同じ凡人です。その言葉を聞いた時には、本当に悩みました。そして残された時間をどう生きればいいのかと、ずいぶん考えたのです。まわりの人は、息子も一人前になったから、すべてを息子にまかせて、のんびりしたらと言 ってくれました。でも、明日が分からない生命だから、のんびりなどできないと思ったのです。今までお世話になった人、ご縁を繋いだ方々に一人でも多くご挨拶してこの世を去りたいと思うようになりました。だから、こちらのお婆ちゃんの十三回忌にも是非お伺いして、今までのご恩に対してお礼を申し上げたかったのです。ひょっとすれば、私の生命は十七回忌の時までいただけるかもしれません。でも明日を頼むより、今日を精いっぱいに生かさせていただけるのが、今の私には何よりもありがたいのです」
こう言って、手を合わせた和尚さん。その姿を見て、「俺とっても感動したよ。あの和尚さんは、命がけで、うちの婆ちゃんにお経をあげてくれたんだよな」と友人は話したのです。
きっと、そこには、生と死を越えた絶対安心の仏さまの世界があらわれていたに違いありません。
(M)

No.028 「人間、捨てたものじゃない」
茅誠司さんと言えば、誰でもできる<小さな親切運動>を提唱なさった東京大学の元学長さん。その茅さんの思い出話が『あの時、あの言葉』(日本経済新聞社刊)という本に載っています。
それは、茅さんが秋田県に住む弟さんの所に預けていた、子供さんを迎えに行った、昭和十八年のことでした。当時の日本は、敗戦の色濃く、人々の心も決して明るい状態ではありませんでした。
子共二人を連れて乗った東京行きの汽車は、超満員で、座るところもありません。茅さんは、通路に新聞紙を敷いて子供たちを座らせ、自分は立ちっぱなしでした。上を見上げると、なんと網棚の上には、若者が寝転がって、これ見よがしに、真っ白い握り飯を見せびらかせながら食べているのです。茅さんは「時代と共に、人間の心もどんどん悪くなる」と腹立たしくなりました。
そんな時、足元に座っていた男のお子さんが、苦しそうに「トイレ」とうなり出したのです。汽車の中は、とても身動きができない状態です。お父さんの茅さんは「どうしよう」と大変焦りました。すると近くに居た誰かが「この子に、トイレをさせてやれ」と叫び、周りの人も声を合わせてくれました。
そのおかげで駅に着くと、窓ガラスが開けられ、坊やは、トイレのあるホームに降ろしてもらえたのです。でも、それだけでは、駅にとり残されるかもしれません。そこで、「あの子のトイレが終わるまで汽車を動かすな」という声が大合唱となって、汽車の中じゅうに響き渡ったそうです。
「その間中、父親の私は何も言えず、ただ頭を下げるだけ、感謝の気持ちでいっぱいだった」と茅さんは話しています。
暗い時代の話だけに、なんとも言えないあたたかさと、人間は決して捨てたものじゃないという思いが伝わってくるのです。苦しい時は、人のことなど構っておれないと、エゴむき出しにする私たち人間ですが、そのもう一つ奥底には、仏さまと同じ、人を思いやる心が宿されているのです。
それから四十数年が過ぎ、男の子は、今では、某大学の教授になっています。 でも、茅さんには、その時のことがついこの間のことのように思い出されるのだそうです。そして、人々の善意が身にしみた茅さんは「誰かが音頭を取れば、みんながそれに同調する。その意味で、人間は、いつでも、どこでも神仏になれる!ただ、そのための音頭を取る必要性を忘れてはならない」と語っています。
<小さな親切運動>の原点は、茅さんのこのような思い出の中にあったのではないでしょうか。 (T)

それは、茅さんが秋田県に住む弟さんの所に預けていた、子供さんを迎えに行った、昭和十八年のことでした。当時の日本は、敗戦の色濃く、人々の心も決して明るい状態ではありませんでした。
子共二人を連れて乗った東京行きの汽車は、超満員で、座るところもありません。茅さんは、通路に新聞紙を敷いて子供たちを座らせ、自分は立ちっぱなしでした。上を見上げると、なんと網棚の上には、若者が寝転がって、これ見よがしに、真っ白い握り飯を見せびらかせながら食べているのです。茅さんは「時代と共に、人間の心もどんどん悪くなる」と腹立たしくなりました。
そんな時、足元に座っていた男のお子さんが、苦しそうに「トイレ」とうなり出したのです。汽車の中は、とても身動きができない状態です。お父さんの茅さんは「どうしよう」と大変焦りました。すると近くに居た誰かが「この子に、トイレをさせてやれ」と叫び、周りの人も声を合わせてくれました。
そのおかげで駅に着くと、窓ガラスが開けられ、坊やは、トイレのあるホームに降ろしてもらえたのです。でも、それだけでは、駅にとり残されるかもしれません。そこで、「あの子のトイレが終わるまで汽車を動かすな」という声が大合唱となって、汽車の中じゅうに響き渡ったそうです。
「その間中、父親の私は何も言えず、ただ頭を下げるだけ、感謝の気持ちでいっぱいだった」と茅さんは話しています。
暗い時代の話だけに、なんとも言えないあたたかさと、人間は決して捨てたものじゃないという思いが伝わってくるのです。苦しい時は、人のことなど構っておれないと、エゴむき出しにする私たち人間ですが、そのもう一つ奥底には、仏さまと同じ、人を思いやる心が宿されているのです。
それから四十数年が過ぎ、男の子は、今では、某大学の教授になっています。 でも、茅さんには、その時のことがついこの間のことのように思い出されるのだそうです。そして、人々の善意が身にしみた茅さんは「誰かが音頭を取れば、みんながそれに同調する。その意味で、人間は、いつでも、どこでも神仏になれる!ただ、そのための音頭を取る必要性を忘れてはならない」と語っています。
<小さな親切運動>の原点は、茅さんのこのような思い出の中にあったのではないでしょうか。 (T)

No.027 「子恩観音」
道ばたで、ふと出会う仏さま。その中で一番多いのがお地蔵さま、その次に目につくのが観音さまだと思います。どちらも、宗派を越えて、人々に親しまれている仏さまですね。ところで、私は今、仏さまと申しましたが、お地蔵さまも、観音さまも、実は仏さまではありません。正確に言えば、いずれも菩薩さま、いわば、仏さまのアシスタント的存在です。でも、だからといって、軽くとらえてはいけません。むしろ、仏さまになろうとして修行している立派な方たちなのです。
しかし、立派だと言ってしまうと、菩薩さまは、私たち凡夫からは、遠い存在になってしまいます。なんといっても、この二つの菩薩さまの魅力は、とびきりの親しみやすさ。私たちが気軽にお願いをしたり、手を合わせることができる所に、人気の秘密があると思います。
お経によりますと、この二つの菩薩さまは、いろんな者に姿を変え、私たちに語りかけ、救いの手を差しのべてくださると言います。そのためでしょうか、人々は、自分たちが形造ったお地蔵さまや観音さまにさえ、いろんなお名前をつけて、お詣りをしています。
つい先日のことでした。たまたま手にした本の中に、『子恩観音』というお名前の観音さまのお姿を見つけました。
子恩とは、「子供の恩」という意味、「親の恩」なら分かるけど、子供の恩なんて、おかしいなと思って、よく見ると、その観音さまの横には、こんな立札があったのです。「私がわたしになるために、わたしに与えられた子供たち。この子供たちに肩身のせまい思いをさせたくないと、ふるい立つ心を与えてくれたのは子供たち。今、合掌をして、ありがとうと拝む。私が本当のわたしになるために、観音さまが私の子供となって、私の前に現われてくださったのだと」
この立札を読んで、私は「こんな観音さまもいらっしゃるのだな」と感激しました。
そのお顔を見れば、どこにでもいるような無邪気な子供の顔。それを彫ったのが、名もない二人の乙女たちと知った時、この乙女たちの願いが心に伝わって来たのです。
「親が子供に感謝されたいと思うなら、まず親は親であることに感謝しなければならない。親であることの喜びを感じたら、子供もまた子供であることの喜びを感じてくれるだろう。」観音さまが、私たちにそう語りかけているような気がしました。そういえば、お地蔵さまにも、よだれ掛けに似た赤い布が掛けられています。あれも、人々のそんな願いが托されているのかもしれませんね。 (J・N)

しかし、立派だと言ってしまうと、菩薩さまは、私たち凡夫からは、遠い存在になってしまいます。なんといっても、この二つの菩薩さまの魅力は、とびきりの親しみやすさ。私たちが気軽にお願いをしたり、手を合わせることができる所に、人気の秘密があると思います。
お経によりますと、この二つの菩薩さまは、いろんな者に姿を変え、私たちに語りかけ、救いの手を差しのべてくださると言います。そのためでしょうか、人々は、自分たちが形造ったお地蔵さまや観音さまにさえ、いろんなお名前をつけて、お詣りをしています。
つい先日のことでした。たまたま手にした本の中に、『子恩観音』というお名前の観音さまのお姿を見つけました。
子恩とは、「子供の恩」という意味、「親の恩」なら分かるけど、子供の恩なんて、おかしいなと思って、よく見ると、その観音さまの横には、こんな立札があったのです。「私がわたしになるために、わたしに与えられた子供たち。この子供たちに肩身のせまい思いをさせたくないと、ふるい立つ心を与えてくれたのは子供たち。今、合掌をして、ありがとうと拝む。私が本当のわたしになるために、観音さまが私の子供となって、私の前に現われてくださったのだと」
この立札を読んで、私は「こんな観音さまもいらっしゃるのだな」と感激しました。
そのお顔を見れば、どこにでもいるような無邪気な子供の顔。それを彫ったのが、名もない二人の乙女たちと知った時、この乙女たちの願いが心に伝わって来たのです。
「親が子供に感謝されたいと思うなら、まず親は親であることに感謝しなければならない。親であることの喜びを感じたら、子供もまた子供であることの喜びを感じてくれるだろう。」観音さまが、私たちにそう語りかけているような気がしました。そういえば、お地蔵さまにも、よだれ掛けに似た赤い布が掛けられています。あれも、人々のそんな願いが托されているのかもしれませんね。 (J・N)

No.026 「写仏 百万枚」
お経を写して書くのは写経、仏さまのお姿を写して描くのを写仏と言います。最近では、この写仏も静かなブームを呼んでいるそうです。
ところである年のお正月、ある和尚さんのところへ、お地蔵さまの絵が描かれた年賀状が舞い込みました。「よく描いてあるなあ」と感心して、その絵をながめていた和尚さんが、さらに見るとよく見ると、そこには“二百五十万三千八百八十二”という番号が書かれてあるのに気づいたのです。
いったい、どうしてそんな番号が書いてあったのでしょう。年賀状の差出し人は、八十三歳になるお婆さん。そのお婆さんが、まだうら若い娘さんの時のことです。「結核性カリエス」という大変な病気に罹りました。あらゆる治療をしてみましたが、回復の見込みはありません。もちろん神仏にも手を合わせました。でも利益はありません。いっそ死のうかと思っていたある晩のこと「私の姿を百万枚写しなさい」という声が彼女の耳に聞こて来ました。これは、彼女が信仰していたお地蔵さまの声だったのです。最初は耳を疑いました。錯覚にしか過ぎないと思いました。でもそれで救われるならと、自分の瞼に浮かぶお地蔵さまの姿を写し始めたのです。
最初のうちは一生懸命でした。それが五十枚、百枚になる頃には、再び疑いの念が生じてきました。しかしここで止めては、元の木阿彌、それに他に助かる道もないし。そう思って自分を励まし、描き続けるうちに、お婆さんは、自分がまだ死んでいないことに気づいたのです。「これがお地蔵さまの教えてくださったご利益かもしれない。こうなれば、死ぬまで描き続けよう」そう思った彼女は、百万枚という気の遠くなるような目標に挑戦する勇気が湧いて来ました。
描けば、描くほど、絵も上手になって来ます。その喜び、その嬉しさ、いつの間にか、自分が絵を描くというより、お地蔵さまが、向こうの方から姿をあらわしてくださるという気持ちにまでなったのです。
そして三十余年、お婆さんは、ついに念願の百万枚のお地蔵さまを描き上げました。「お医者さまに、再起不能と宣言された時から、それまでの私は死んでしまったのかもしれません。でも、それがこうして今も生命あるのは、本当にお地蔵さまのお蔭です。」そう語るお婆さんは、その後も二百万、三百万と写仏をし、お地蔵さまと一緒に、人生の旅を続けているのです。 (M・N)

ところである年のお正月、ある和尚さんのところへ、お地蔵さまの絵が描かれた年賀状が舞い込みました。「よく描いてあるなあ」と感心して、その絵をながめていた和尚さんが、さらに見るとよく見ると、そこには“二百五十万三千八百八十二”という番号が書かれてあるのに気づいたのです。
いったい、どうしてそんな番号が書いてあったのでしょう。年賀状の差出し人は、八十三歳になるお婆さん。そのお婆さんが、まだうら若い娘さんの時のことです。「結核性カリエス」という大変な病気に罹りました。あらゆる治療をしてみましたが、回復の見込みはありません。もちろん神仏にも手を合わせました。でも利益はありません。いっそ死のうかと思っていたある晩のこと「私の姿を百万枚写しなさい」という声が彼女の耳に聞こて来ました。これは、彼女が信仰していたお地蔵さまの声だったのです。最初は耳を疑いました。錯覚にしか過ぎないと思いました。でもそれで救われるならと、自分の瞼に浮かぶお地蔵さまの姿を写し始めたのです。
最初のうちは一生懸命でした。それが五十枚、百枚になる頃には、再び疑いの念が生じてきました。しかしここで止めては、元の木阿彌、それに他に助かる道もないし。そう思って自分を励まし、描き続けるうちに、お婆さんは、自分がまだ死んでいないことに気づいたのです。「これがお地蔵さまの教えてくださったご利益かもしれない。こうなれば、死ぬまで描き続けよう」そう思った彼女は、百万枚という気の遠くなるような目標に挑戦する勇気が湧いて来ました。
描けば、描くほど、絵も上手になって来ます。その喜び、その嬉しさ、いつの間にか、自分が絵を描くというより、お地蔵さまが、向こうの方から姿をあらわしてくださるという気持ちにまでなったのです。
そして三十余年、お婆さんは、ついに念願の百万枚のお地蔵さまを描き上げました。「お医者さまに、再起不能と宣言された時から、それまでの私は死んでしまったのかもしれません。でも、それがこうして今も生命あるのは、本当にお地蔵さまのお蔭です。」そう語るお婆さんは、その後も二百万、三百万と写仏をし、お地蔵さまと一緒に、人生の旅を続けているのです。 (M・N)

No.025 「父との仏縁」
「縁は異なもの味なもの」私たちは、まさにその縁によって、色々な人生模様を作って行きます。お釈迦さまが、「この世の存在はすべて縁によって起り、それ独自で存在するものはない」と『縁起の法』を繰り返し説いておられます。私たちにとって、その縁えにし
を、正しく知る事が、まさに人生をより尊いものにするのだと言えます。
私は、父親の顔を知りません。覚えていないと言う方が正確でしょう。私の父は、三十三歳の若さでこの世を去りました。今年、私は三十五歳を迎え、年齢では父を超えた事になります。その父の、三十三回忌法事を営みました。私の年齢で、親の三十三回忌を行なう事もめずらしいと思うのですが、子が出家の身となってみずから法要を営むことは、もっと稀な事かもしれません。
当日の参列者は、身の近い数人の者だけでしたが、一緒に唱えるお経の声が、私にはとても心よく響き、亡き父もさぞかし喜んでいるのだろうと感じられたものです。「おそらく亡き父も、私が出家をして、自分の法事を営む事など、おそらく考えてもいなかっただろう」そう思いながら、ご回向を進める中で、私はふと、自分の出家の縁は、この父との死別にあるのではないかと思ったのです。
これまでの私は、尼僧にまでなった母親の、熱心な信仰の姿に影響されて、出家の道に入ったと考えていました。そんな訳ですから、母の願いに叶うお坊さんにならなければと、気負いにも似た使命感をずっと持って来ました。
しかし、母の強盛な信仰は、若くして夫と死別をした悲しみ、母子家庭という経済的に困難な生活の中から育くまれて来たという事実を、私は三人の子供の父親になって、始めて気づかされたのです。さらに、母がその信仰を自分の心の支えにするばかりではなく、多くの人々にその心をすすめ導く出家の道を、父の死という縁の中から切り開いて来たその姿に、私は今、頭が下がります。
考えてみれば、父親の居る家庭がうらやましく、さびしい思いをした事、友達がお父さんの自慢話をする中に入っていけなかったくやしさ、様々な思いが幼い頃の自分の姿とともに思い出されてきます。時として、どうにもならない自分のさびしさを、母にぶつけた事もありました。しかし、そんな色々な事が、現在の私に成長させて くれたのだと考えられる様になりました。この世では縁の薄かった父でしたが、 その少ない父との縁の中に、今の私を支えている尊い縁(えにし)がある事を、 あらためて知らされたご法事を終えたのです。 (W)

私は、父親の顔を知りません。覚えていないと言う方が正確でしょう。私の父は、三十三歳の若さでこの世を去りました。今年、私は三十五歳を迎え、年齢では父を超えた事になります。その父の、三十三回忌法事を営みました。私の年齢で、親の三十三回忌を行なう事もめずらしいと思うのですが、子が出家の身となってみずから法要を営むことは、もっと稀な事かもしれません。
当日の参列者は、身の近い数人の者だけでしたが、一緒に唱えるお経の声が、私にはとても心よく響き、亡き父もさぞかし喜んでいるのだろうと感じられたものです。「おそらく亡き父も、私が出家をして、自分の法事を営む事など、おそらく考えてもいなかっただろう」そう思いながら、ご回向を進める中で、私はふと、自分の出家の縁は、この父との死別にあるのではないかと思ったのです。
これまでの私は、尼僧にまでなった母親の、熱心な信仰の姿に影響されて、出家の道に入ったと考えていました。そんな訳ですから、母の願いに叶うお坊さんにならなければと、気負いにも似た使命感をずっと持って来ました。
しかし、母の強盛な信仰は、若くして夫と死別をした悲しみ、母子家庭という経済的に困難な生活の中から育くまれて来たという事実を、私は三人の子供の父親になって、始めて気づかされたのです。さらに、母がその信仰を自分の心の支えにするばかりではなく、多くの人々にその心をすすめ導く出家の道を、父の死という縁の中から切り開いて来たその姿に、私は今、頭が下がります。
考えてみれば、父親の居る家庭がうらやましく、さびしい思いをした事、友達がお父さんの自慢話をする中に入っていけなかったくやしさ、様々な思いが幼い頃の自分の姿とともに思い出されてきます。時として、どうにもならない自分のさびしさを、母にぶつけた事もありました。しかし、そんな色々な事が、現在の私に成長させて くれたのだと考えられる様になりました。この世では縁の薄かった父でしたが、 その少ない父との縁の中に、今の私を支えている尊い縁(えにし)がある事を、 あらためて知らされたご法事を終えたのです。 (W)

No.024 「布教と宣伝の違い」
先日のことです。自坊に、ある大手新聞の広告社と名乗る人から電話がかかって来ました。「今回、うちの新聞で、お彼岸の特集記事を組むことになりました。つきましては、お宅のお寺さまにも協賛の広告をお願いしたいのですが…」という依頼です。
「またか」と思った私は、いつものように、即座に断りの返事を口にしました。でも今回は、相手も負けてはいませんでした。「仏教の行事を社会に知らせることは、今の時代、とても大切な布教だと思いますけれども」さすがはセールスマン。こちらのウィークポイントを突いてきます。数分間にもわたる押し問答の末、こちらが出した切り札は「実は、私は住職ではないので、ご返事しかねます。とりあえず、ほかのお寺さんをあたってください」というかなり、情けない逃げの手でした。
なんとかその場は切り抜けたものの、私は電話の相手とのやりとりが、とても気になっていました。というのもあるヨーロッパの学者が言っていた、こんな言葉を思い出したからです。「確かに仏教は素晴らしい教えではある。しかしキリスト教に比べると、今一つ欠けたところがある。それは仏教には教えを人々に伝え、共に分かちあい、共に活動しようとする意欲に乏しい点である」
このある種痛烈な批判は、今のお寺の一面を指摘していると言えなくもありません。あまりにも、布教活動に消極的なお寺の布教活動のあり方があるとすれば、それはまさに、社会から仏教を忘れさせてしまいかねない要因の一つになってしまいます。
しかし、私はあえて「しかし」と言いたいのです。
つまり仏教は、宣伝の宗教ではないのです。人間の、静かな思索の中から生まれた仏の教えは、やたら目や耳に洪水のように流れ込ませることによって今日まで広まってきたのではありません。むしろ、目や耳に触れるものによって、心を乱されてはならないと説かれたのがお釈迦さまであります。そう考え直して、あらためてマスコミ界を見ると、やたらご利益談義や奇跡を誇る、いわゆる宗教広告が目につき過ぎます。宣伝と布教とは、まったく違うのだと気がつきます。
宣伝は、当方の存在を一方的にアピールするものですが、布教とは相手のためを思って、仏の教えを広めることです。
お釈迦さまは、四十五年の間、みずからの足で歩き、法を説き続けられましたが、それは、常に人々の悩みに対して、ひとつひとつその答えを出していくというものでした。
決して、これ見よがしの押しつけではありませんでした。
確かに現代は、宣伝の時代です。社会に対し、仏の教えを広めることは、とても大切なことです。でも一時的に燃えさかる火のような、煽りに煽ったエセ信仰などよりも、たゆまない水の流れのような信心が大切ではないでしょうか。人々の心にしみるような布教、そんな布教活動のあり方を今こそ私たちは、真剣に考えるべきでは ないでしょうか。 (M)

「またか」と思った私は、いつものように、即座に断りの返事を口にしました。でも今回は、相手も負けてはいませんでした。「仏教の行事を社会に知らせることは、今の時代、とても大切な布教だと思いますけれども」さすがはセールスマン。こちらのウィークポイントを突いてきます。数分間にもわたる押し問答の末、こちらが出した切り札は「実は、私は住職ではないので、ご返事しかねます。とりあえず、ほかのお寺さんをあたってください」というかなり、情けない逃げの手でした。
なんとかその場は切り抜けたものの、私は電話の相手とのやりとりが、とても気になっていました。というのもあるヨーロッパの学者が言っていた、こんな言葉を思い出したからです。「確かに仏教は素晴らしい教えではある。しかしキリスト教に比べると、今一つ欠けたところがある。それは仏教には教えを人々に伝え、共に分かちあい、共に活動しようとする意欲に乏しい点である」
このある種痛烈な批判は、今のお寺の一面を指摘していると言えなくもありません。あまりにも、布教活動に消極的なお寺の布教活動のあり方があるとすれば、それはまさに、社会から仏教を忘れさせてしまいかねない要因の一つになってしまいます。
しかし、私はあえて「しかし」と言いたいのです。
つまり仏教は、宣伝の宗教ではないのです。人間の、静かな思索の中から生まれた仏の教えは、やたら目や耳に洪水のように流れ込ませることによって今日まで広まってきたのではありません。むしろ、目や耳に触れるものによって、心を乱されてはならないと説かれたのがお釈迦さまであります。そう考え直して、あらためてマスコミ界を見ると、やたらご利益談義や奇跡を誇る、いわゆる宗教広告が目につき過ぎます。宣伝と布教とは、まったく違うのだと気がつきます。
宣伝は、当方の存在を一方的にアピールするものですが、布教とは相手のためを思って、仏の教えを広めることです。
お釈迦さまは、四十五年の間、みずからの足で歩き、法を説き続けられましたが、それは、常に人々の悩みに対して、ひとつひとつその答えを出していくというものでした。
決して、これ見よがしの押しつけではありませんでした。
確かに現代は、宣伝の時代です。社会に対し、仏の教えを広めることは、とても大切なことです。でも一時的に燃えさかる火のような、煽りに煽ったエセ信仰などよりも、たゆまない水の流れのような信心が大切ではないでしょうか。人々の心にしみるような布教、そんな布教活動のあり方を今こそ私たちは、真剣に考えるべきでは ないでしょうか。 (M)

No.023 「説教はライブで」
スイカといえば、夏の果物でした。ところが近頃では五月頃から出回っています。いえ、真冬でも、果物屋さんの店頭に並んでいます。
子供の頃は井戸で冷したスイカを、セミの鳴き声を聞きながら、かぶりついたことを思い出しながら、「世の中、変わりましたね」と話しました。もちろん、今でも夏にスイカを食べない訳ではありません。でも、スイカに対する感激が、昔と全然ちがうのです。
いつでも有るということは、私たちから「待つ」という心を失わせてしまいました。待つということは、つらいことです。しかし、一面では楽しみでもあるということも知らねばなりません。
「待つ」という心の働きによって、私たちの胸には、夢と希望がふくらむのです。そして、待った後に出会ったという感激が、私たちの人生を豊かにさえするのです。
先日、お説教に出かけたお寺さんで、一人のお爺さんが、私の話を録音していました。
「近頃は、こんな便利なものができたから、ありがたいですね」そういうお爺さんは「このお話を、家に帰って家族に聞かせます」と言いました。熱心な人だなと感心していると「でも、こんな道具ができたおかげで、一緒にお寺に行こうと誘っても、後でテープを聞くから、わざわざお寺に行かなくてもいいと断られた」と、ぼやきました。
「テープなら、自分の家で寝ころんでも聞けるし、足もしびれませんからね」この話を聞きながら、便利というのは、そんなマイナスの面もあるのかと思ったのです。
ところが、その時、横にいた青年が「お説教は、やっぱりライブでなくちゃあ」と言ったのです。お爺さんがびっくりして「ライブってなんですか」と尋ねました。「生演奏のことをライブって言うんだよ。いくらいい機械でも、機械は機械、心までは伝わってこないからね。これからはなんといっても生の時代だよ。ビールも生だし、お金も現生が最高だからね」と笑わせます。
これを聞いた私は、いいことを言うなと思いました。これからは、手作りこそ求められる時代だと思うからです。
一年中出回っている野菜や果物に飽いているのは、そこには新鮮さという実感がないからでしょう。自然と共に生きる気持ちがなければ、私たちは生き生きとした心まで失ってしまうような、そんな気がしてなりません。 (T)

子供の頃は井戸で冷したスイカを、セミの鳴き声を聞きながら、かぶりついたことを思い出しながら、「世の中、変わりましたね」と話しました。もちろん、今でも夏にスイカを食べない訳ではありません。でも、スイカに対する感激が、昔と全然ちがうのです。
いつでも有るということは、私たちから「待つ」という心を失わせてしまいました。待つということは、つらいことです。しかし、一面では楽しみでもあるということも知らねばなりません。
「待つ」という心の働きによって、私たちの胸には、夢と希望がふくらむのです。そして、待った後に出会ったという感激が、私たちの人生を豊かにさえするのです。
先日、お説教に出かけたお寺さんで、一人のお爺さんが、私の話を録音していました。
「近頃は、こんな便利なものができたから、ありがたいですね」そういうお爺さんは「このお話を、家に帰って家族に聞かせます」と言いました。熱心な人だなと感心していると「でも、こんな道具ができたおかげで、一緒にお寺に行こうと誘っても、後でテープを聞くから、わざわざお寺に行かなくてもいいと断られた」と、ぼやきました。
「テープなら、自分の家で寝ころんでも聞けるし、足もしびれませんからね」この話を聞きながら、便利というのは、そんなマイナスの面もあるのかと思ったのです。
ところが、その時、横にいた青年が「お説教は、やっぱりライブでなくちゃあ」と言ったのです。お爺さんがびっくりして「ライブってなんですか」と尋ねました。「生演奏のことをライブって言うんだよ。いくらいい機械でも、機械は機械、心までは伝わってこないからね。これからはなんといっても生の時代だよ。ビールも生だし、お金も現生が最高だからね」と笑わせます。
これを聞いた私は、いいことを言うなと思いました。これからは、手作りこそ求められる時代だと思うからです。
一年中出回っている野菜や果物に飽いているのは、そこには新鮮さという実感がないからでしょう。自然と共に生きる気持ちがなければ、私たちは生き生きとした心まで失ってしまうような、そんな気がしてなりません。 (T)

No.022 「報復の虚しさ」
「まこと怨みごころは、いかなるすべを持つとも、怨みを懐くその日まで、ひとの世には止みがたし。うらみなさによりてのみ、うらみはついに消ゆるべし。こは易らざる真理なり」(友松円諦 訳)
これは法句経というお経の中にある言葉です。私たちにとって、怨みほどやっかいなものはありません。恨むまいと思っても、心の中から、なかなか消えてくれないのが怨みです。
戦争が終わって五十年以上も経った今も、朝鮮人慰安婦問題をはじめ、いろんな心の傷痕が解決されないままに残っています。その人たちの味わわされた苦悩、舐めさせられた屈辱を考えれば、何ひとつ許せないのが当然だと思います。
「この怨みを晴らさなければ、死んでも死にきれない」という気持ちになるのも、無理からぬことでしょう。でも、願い叶って、その目的を遂げてしまった時、人々の心には満足感は、おとずれるのでしょうか。
ここに、こんな記録があります。
一九六〇年五月、ナチスの親衛隊長だったアイヒマンが、彼を追い求めたイスラエルの謀報機関によって逮捕された時のことです。彼は、あの第二次世界大戦の時、ユダヤの人々を迫害し、ありとあらゆる暴虐を加えた人間です。ユダヤの人々のナチスに対する怨みは、言葉には尽くせないものがありました。そこで作家でもある某ルポライターが、謀報機関の人に、「アイヒマンを捕まえた時どんな気持ちでしたか」と尋ねたのです。すると、こんな答えが返ってきました。「驚きと期待はずれが入り混じった気持ちだね。六百万人もの同胞を殺した男だ。獣のような男を想像していたよ。でも、目の前にいるのは、ひ弱で、ただビクビクしている男に過ぎなかった。捕まえた時以外、だれも彼には指一本触れようとしないのに、彼は今にも殺されるのではないかと怯えきっていた。食事を与えれば毒殺されるのではないかと震え、ヒゲを剃ってやろうとすれば、ノドをかき切られるのではないかと震え、散歩させてやろうとすれば、外で銃殺されると怯えるんだ。こんな臆病者の、自尊心のかけらもないような男に、同胞が殺されたのかと思うと、怨むというよりも、情けない気持ちでいっぱいになったよ」
この記事を読んで、私は〈報復〉という観念・行為の虚しさを感じました。「うらみなさによりて、うらみはついに消ゆるべし。こは易らざる真理なり」という、お釈迦さまの声が、二千年という時代を超えて、今現代の世界に聞こえて来る気がしました。自分の論理だけを主張した、報復の繰り返しなどによって、決して、世界に平和は、 おとずれません。 (J・N)

これは法句経というお経の中にある言葉です。私たちにとって、怨みほどやっかいなものはありません。恨むまいと思っても、心の中から、なかなか消えてくれないのが怨みです。
戦争が終わって五十年以上も経った今も、朝鮮人慰安婦問題をはじめ、いろんな心の傷痕が解決されないままに残っています。その人たちの味わわされた苦悩、舐めさせられた屈辱を考えれば、何ひとつ許せないのが当然だと思います。
「この怨みを晴らさなければ、死んでも死にきれない」という気持ちになるのも、無理からぬことでしょう。でも、願い叶って、その目的を遂げてしまった時、人々の心には満足感は、おとずれるのでしょうか。
ここに、こんな記録があります。
一九六〇年五月、ナチスの親衛隊長だったアイヒマンが、彼を追い求めたイスラエルの謀報機関によって逮捕された時のことです。彼は、あの第二次世界大戦の時、ユダヤの人々を迫害し、ありとあらゆる暴虐を加えた人間です。ユダヤの人々のナチスに対する怨みは、言葉には尽くせないものがありました。そこで作家でもある某ルポライターが、謀報機関の人に、「アイヒマンを捕まえた時どんな気持ちでしたか」と尋ねたのです。すると、こんな答えが返ってきました。「驚きと期待はずれが入り混じった気持ちだね。六百万人もの同胞を殺した男だ。獣のような男を想像していたよ。でも、目の前にいるのは、ひ弱で、ただビクビクしている男に過ぎなかった。捕まえた時以外、だれも彼には指一本触れようとしないのに、彼は今にも殺されるのではないかと怯えきっていた。食事を与えれば毒殺されるのではないかと震え、ヒゲを剃ってやろうとすれば、ノドをかき切られるのではないかと震え、散歩させてやろうとすれば、外で銃殺されると怯えるんだ。こんな臆病者の、自尊心のかけらもないような男に、同胞が殺されたのかと思うと、怨むというよりも、情けない気持ちでいっぱいになったよ」
この記事を読んで、私は〈報復〉という観念・行為の虚しさを感じました。「うらみなさによりて、うらみはついに消ゆるべし。こは易らざる真理なり」という、お釈迦さまの声が、二千年という時代を超えて、今現代の世界に聞こえて来る気がしました。自分の論理だけを主張した、報復の繰り返しなどによって、決して、世界に平和は、 おとずれません。 (J・N)

No.021 「病院の中での法衣姿」
入院中の檀家さんを、お見舞いに行った時のことです。受付に行くと、係の人たちが、こちらをジロジロ見ます。「感じが悪いなあ」と思いながら通り過ぎようとすると「ちょっと、ちょっと」と、呼び止められました。「あまり目立たないようにしてください。他の患者さんに、影響しますから」
そう言われて、受付での “ジロジロ” の原因は、私の衣装にあることが判明しました。お参りの途中だった私は、黒い墨染の法衣姿のままだったのです。「すみません」と謝ったものの、内心では「坊さんが坊さんの格好をして来て、何が悪いんだ」と言い返したくなりました。
世間からは、坊さんイコールお葬式。時には、不吉で、縁起が悪いように思われることさえあります。そんな人々の気持ちがあるということも、わからない訳ではありませんが、以前私が読んだことのある、某仏教雑誌のコラムに、こんな記述がありました。
『仏教者が、病院や老人ホームに出入りすることが『縁起が悪い』とか『まだ早い』などと言われることは、本来おかしいことである。死に臨んだ人や、お年寄りが、真に語り掛けられるのは、仏さまだけであろう。誰もその人の心の中をわかることができなくても、仏さまは、わかってくださるはずである。したがって檀信徒の方が入院されたり、老人ホームに入所されたならば、積極的に出向いて、その人のお話を聞いていただきたい。ただ手を握り、顔を見つめて、話はなされることを聞き、うなずくだけでもよいのである』と。
この意見は、世俗的な常識とは、逆の意見ではあります。しかし私は、本来のお坊さんは、かくあるべきだと思っています。〈死〉は確かに私たちにとって、一番の苦しみ、恐怖の対象であります。だからこそ、最も心の安らぎが必要な時であるはずなのに、逆に拒否反応を示される。これはまことに悲しい現実だという他ありません。
聞けば、キリスト教の牧師さんは、臨終ま近かになった信者さんの枕元に立ち合うそうです。それは、人が死ぬ前に、「自分がこの世で犯した罪を、すべて懺悔しなければならない」という、信仰上の理由からだそうですが、病院側はこれを許可していると言います。それなら我々坊さんの方も、ひと踏ん張りしなければなりません。
最近では、病人の心の相談役とも言える“ホスピス”の制度が関心を集めています。これからのお坊さんは、人が死んでからよりも、死の直前に信頼を集め得る仕事をしなければならないでしょう。そうなれば、黒い法衣を着て病院に入って行っても、むしろ、それが信頼のシンボルになるに違いないと思うのです。 (M・N)

そう言われて、受付での “ジロジロ” の原因は、私の衣装にあることが判明しました。お参りの途中だった私は、黒い墨染の法衣姿のままだったのです。「すみません」と謝ったものの、内心では「坊さんが坊さんの格好をして来て、何が悪いんだ」と言い返したくなりました。
世間からは、坊さんイコールお葬式。時には、不吉で、縁起が悪いように思われることさえあります。そんな人々の気持ちがあるということも、わからない訳ではありませんが、以前私が読んだことのある、某仏教雑誌のコラムに、こんな記述がありました。
『仏教者が、病院や老人ホームに出入りすることが『縁起が悪い』とか『まだ早い』などと言われることは、本来おかしいことである。死に臨んだ人や、お年寄りが、真に語り掛けられるのは、仏さまだけであろう。誰もその人の心の中をわかることができなくても、仏さまは、わかってくださるはずである。したがって檀信徒の方が入院されたり、老人ホームに入所されたならば、積極的に出向いて、その人のお話を聞いていただきたい。ただ手を握り、顔を見つめて、話はなされることを聞き、うなずくだけでもよいのである』と。
この意見は、世俗的な常識とは、逆の意見ではあります。しかし私は、本来のお坊さんは、かくあるべきだと思っています。〈死〉は確かに私たちにとって、一番の苦しみ、恐怖の対象であります。だからこそ、最も心の安らぎが必要な時であるはずなのに、逆に拒否反応を示される。これはまことに悲しい現実だという他ありません。
聞けば、キリスト教の牧師さんは、臨終ま近かになった信者さんの枕元に立ち合うそうです。それは、人が死ぬ前に、「自分がこの世で犯した罪を、すべて懺悔しなければならない」という、信仰上の理由からだそうですが、病院側はこれを許可していると言います。それなら我々坊さんの方も、ひと踏ん張りしなければなりません。
最近では、病人の心の相談役とも言える“ホスピス”の制度が関心を集めています。これからのお坊さんは、人が死んでからよりも、死の直前に信頼を集め得る仕事をしなければならないでしょう。そうなれば、黒い法衣を着て病院に入って行っても、むしろ、それが信頼のシンボルになるに違いないと思うのです。 (M・N)