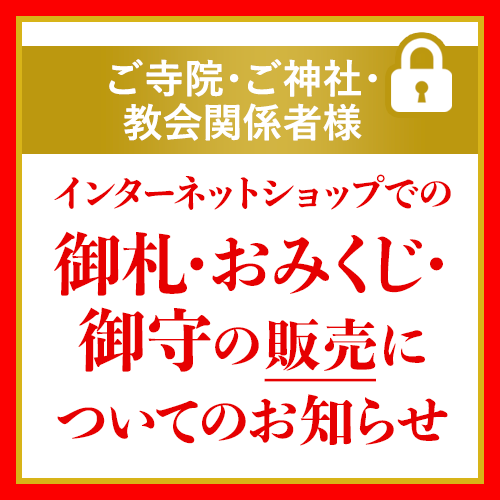蓮の実通信
No.028 「人間、捨てたものじゃない」
茅誠司さんと言えば、誰でもできる<小さな親切運動>を提唱なさった東京大学の元学長さん。その茅さんの思い出話が『あの時、あの言葉』(日本経済新聞社刊)という本に載っています。
それは、茅さんが秋田県に住む弟さんの所に預けていた、子供さんを迎えに行った、昭和十八年のことでした。当時の日本は、敗戦の色濃く、人々の心も決して明るい状態ではありませんでした。
子共二人を連れて乗った東京行きの汽車は、超満員で、座るところもありません。茅さんは、通路に新聞紙を敷いて子供たちを座らせ、自分は立ちっぱなしでした。上を見上げると、なんと網棚の上には、若者が寝転がって、これ見よがしに、真っ白い握り飯を見せびらかせながら食べているのです。茅さんは「時代と共に、人間の心もどんどん悪くなる」と腹立たしくなりました。
そんな時、足元に座っていた男のお子さんが、苦しそうに「トイレ」とうなり出したのです。汽車の中は、とても身動きができない状態です。お父さんの茅さんは「どうしよう」と大変焦りました。すると近くに居た誰かが「この子に、トイレをさせてやれ」と叫び、周りの人も声を合わせてくれました。
そのおかげで駅に着くと、窓ガラスが開けられ、坊やは、トイレのあるホームに降ろしてもらえたのです。でも、それだけでは、駅にとり残されるかもしれません。そこで、「あの子のトイレが終わるまで汽車を動かすな」という声が大合唱となって、汽車の中じゅうに響き渡ったそうです。
「その間中、父親の私は何も言えず、ただ頭を下げるだけ、感謝の気持ちでいっぱいだった」と茅さんは話しています。
暗い時代の話だけに、なんとも言えないあたたかさと、人間は決して捨てたものじゃないという思いが伝わってくるのです。苦しい時は、人のことなど構っておれないと、エゴむき出しにする私たち人間ですが、そのもう一つ奥底には、仏さまと同じ、人を思いやる心が宿されているのです。
それから四十数年が過ぎ、男の子は、今では、某大学の教授になっています。 でも、茅さんには、その時のことがついこの間のことのように思い出されるのだそうです。そして、人々の善意が身にしみた茅さんは「誰かが音頭を取れば、みんながそれに同調する。その意味で、人間は、いつでも、どこでも神仏になれる!ただ、そのための音頭を取る必要性を忘れてはならない」と語っています。
<小さな親切運動>の原点は、茅さんのこのような思い出の中にあったのではないでしょうか。 (T)

それは、茅さんが秋田県に住む弟さんの所に預けていた、子供さんを迎えに行った、昭和十八年のことでした。当時の日本は、敗戦の色濃く、人々の心も決して明るい状態ではありませんでした。
子共二人を連れて乗った東京行きの汽車は、超満員で、座るところもありません。茅さんは、通路に新聞紙を敷いて子供たちを座らせ、自分は立ちっぱなしでした。上を見上げると、なんと網棚の上には、若者が寝転がって、これ見よがしに、真っ白い握り飯を見せびらかせながら食べているのです。茅さんは「時代と共に、人間の心もどんどん悪くなる」と腹立たしくなりました。
そんな時、足元に座っていた男のお子さんが、苦しそうに「トイレ」とうなり出したのです。汽車の中は、とても身動きができない状態です。お父さんの茅さんは「どうしよう」と大変焦りました。すると近くに居た誰かが「この子に、トイレをさせてやれ」と叫び、周りの人も声を合わせてくれました。
そのおかげで駅に着くと、窓ガラスが開けられ、坊やは、トイレのあるホームに降ろしてもらえたのです。でも、それだけでは、駅にとり残されるかもしれません。そこで、「あの子のトイレが終わるまで汽車を動かすな」という声が大合唱となって、汽車の中じゅうに響き渡ったそうです。
「その間中、父親の私は何も言えず、ただ頭を下げるだけ、感謝の気持ちでいっぱいだった」と茅さんは話しています。
暗い時代の話だけに、なんとも言えないあたたかさと、人間は決して捨てたものじゃないという思いが伝わってくるのです。苦しい時は、人のことなど構っておれないと、エゴむき出しにする私たち人間ですが、そのもう一つ奥底には、仏さまと同じ、人を思いやる心が宿されているのです。
それから四十数年が過ぎ、男の子は、今では、某大学の教授になっています。 でも、茅さんには、その時のことがついこの間のことのように思い出されるのだそうです。そして、人々の善意が身にしみた茅さんは「誰かが音頭を取れば、みんながそれに同調する。その意味で、人間は、いつでも、どこでも神仏になれる!ただ、そのための音頭を取る必要性を忘れてはならない」と語っています。
<小さな親切運動>の原点は、茅さんのこのような思い出の中にあったのではないでしょうか。 (T)