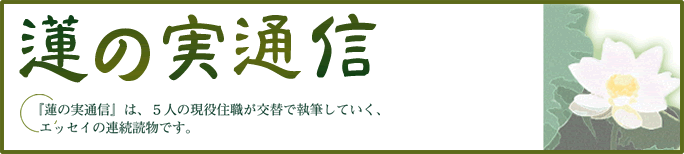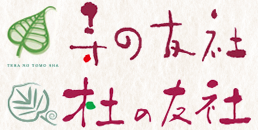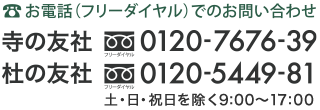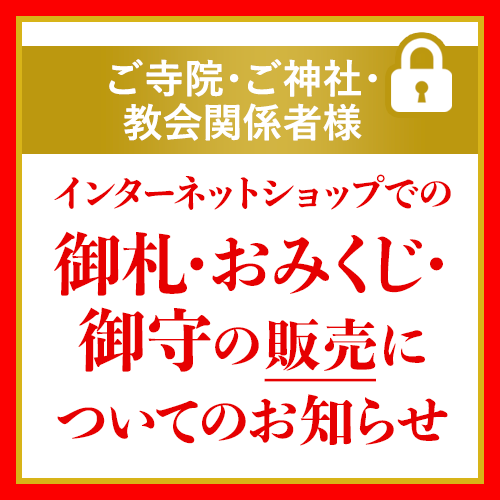蓮の実通信
No.030 「消えざる恨み」
他人に冷たい仕打ちをされた時、私たちは「死んでも忘れるものか」と相手を怨むことがあります。怨みは、古今東西、たいそう始末の悪いもので、人間の歴史は、その怨みの繰り返しと言われるほどです。
試みに、お経をひもといてみると、お釈迦さまのこんな言葉に出会いました。
『<彼、われを罵り、彼、われを打ちたり。彼、われを打ち負かし、彼、われを奪えり>かくのごとく心執する人々に、怨みは、ついにやむことなし』
きっとお釈迦さまのもとにも、忘れられない怨みをかかえた人が、自分の胸の内を聞いて欲しいと集まって来たことでしょう。そんな悩める人々に、お釈迦さまは、どのように答えられたのでしょうか。
私は、そんな思いにふけりながら、ある戦争の未亡人のことを思い出したのです。
敗戦後しばらくは、国民の誰もが、食糧の危機にさらされた時期です。二人の幼な児をかかえた彼女の毎日は「この子たちを、ひもじいめに遭わせたくない」という思いだけでした。売れる物は全部売り、とうとう底をついてしまった時、彼女は最後の綱と、本家の門を叩いたのです。ところが対応に出た義兄嫁に、ケンカもホロロに「その格好は何なの。食べ物が欲しいなら、裏にまわって納屋のカボチャでも持っていくがいいわ」と冷たくあしらわれた彼女は、くやしさのあまり、二人の子の手をぎゅっと握りしめ、逃げるようにして本家を後にしたそうです。
「こうなったら、誰も頼るものか。いつか本家を見返してやる!」そう誓って生きて来た三十余年、その甲斐あって二人の子も立派に成長し、孫にも恵まれ、家も建て直すことができるようになりました。そして、古い家を解体する時、彼女はお経をあげてくださいと、私のいるお寺にやって来たのです。
「考えてみれば、この家は私の怨みの思いでいっぱいです。義兄嫁のあの言葉があればこそ、今日があるのですが、それを許してしまえるほど、私は人間ができていません」と語る彼女の記憶の中に、今なお残るあの日の屈辱。それを払おうとして払えないと思い知った時、彼女はやはり仏さまのお慈悲にすがるしかないと思ったのでしょう。
『まことに、怨みごころは、いかなるすべを持つとも怨みをいだくその日まで、人の世にはやみがたし。怨みなさによりてのみ、怨みはついに消ゆるべし。これかわらざる真理(まこと)なり』お釈迦さまは、彼女の心を見透かすかのように、こう語りかけていらっしゃるのです。
(W)
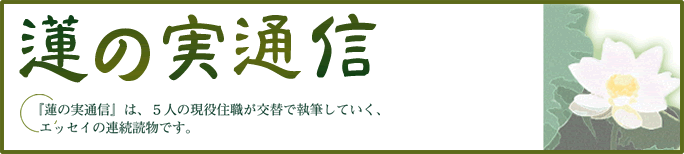
試みに、お経をひもといてみると、お釈迦さまのこんな言葉に出会いました。
『<彼、われを罵り、彼、われを打ちたり。彼、われを打ち負かし、彼、われを奪えり>かくのごとく心執する人々に、怨みは、ついにやむことなし』
きっとお釈迦さまのもとにも、忘れられない怨みをかかえた人が、自分の胸の内を聞いて欲しいと集まって来たことでしょう。そんな悩める人々に、お釈迦さまは、どのように答えられたのでしょうか。
私は、そんな思いにふけりながら、ある戦争の未亡人のことを思い出したのです。
敗戦後しばらくは、国民の誰もが、食糧の危機にさらされた時期です。二人の幼な児をかかえた彼女の毎日は「この子たちを、ひもじいめに遭わせたくない」という思いだけでした。売れる物は全部売り、とうとう底をついてしまった時、彼女は最後の綱と、本家の門を叩いたのです。ところが対応に出た義兄嫁に、ケンカもホロロに「その格好は何なの。食べ物が欲しいなら、裏にまわって納屋のカボチャでも持っていくがいいわ」と冷たくあしらわれた彼女は、くやしさのあまり、二人の子の手をぎゅっと握りしめ、逃げるようにして本家を後にしたそうです。
「こうなったら、誰も頼るものか。いつか本家を見返してやる!」そう誓って生きて来た三十余年、その甲斐あって二人の子も立派に成長し、孫にも恵まれ、家も建て直すことができるようになりました。そして、古い家を解体する時、彼女はお経をあげてくださいと、私のいるお寺にやって来たのです。
「考えてみれば、この家は私の怨みの思いでいっぱいです。義兄嫁のあの言葉があればこそ、今日があるのですが、それを許してしまえるほど、私は人間ができていません」と語る彼女の記憶の中に、今なお残るあの日の屈辱。それを払おうとして払えないと思い知った時、彼女はやはり仏さまのお慈悲にすがるしかないと思ったのでしょう。
『まことに、怨みごころは、いかなるすべを持つとも怨みをいだくその日まで、人の世にはやみがたし。怨みなさによりてのみ、怨みはついに消ゆるべし。これかわらざる真理(まこと)なり』お釈迦さまは、彼女の心を見透かすかのように、こう語りかけていらっしゃるのです。
(W)